留学中の食事ってどんなの?
美味しくなかったらどうしよう
と心配される方も多いのではないのでしょうか。
私も息子をアメリカのボーディングスクールに送り出した当初、
- ちゃんと食べているかな
- 和食が恋しくなっていないかな
と心配で仕方ありませんでした。
この記事では、「ボーディングスクールのリアルな食事事情」を
実体験を交えながらわかりやすく紹介します。

ワンダがボーディングスクールの食堂事情をしっかりリサーチしてきました!
留学を控えるご家庭にとって、“食”を通じて安心できるきっかけになれば嬉しいです。
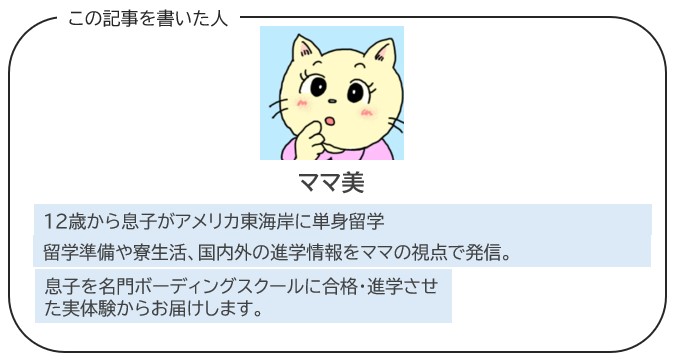
ボーディングスクールの食事事情とは
食堂(Dining Hall)の仕組み



ボーディングスクールの食事は、基本的に「食堂(Dining Hall)」で提供されます。
1日3食(朝・昼・夜)が学校内で完結し、
食堂は単なる「食べる場所」ではなく、生徒や先生との交流の場。
食事中のスマホ使用を禁止している学校も多く、“会話を通じて学ぶ場”としての文化が根づいています。
多くの食堂には生徒たちの国籍の国旗が飾ってあり国を超えた絆を育む場所となってます。
食事が“授業の延長線”にあるのが特徴です。
食事の時間
食事時間は、学校によって異なりますが一般的に以下のようなスケジュールです。
| 食事 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|
| 朝食 | 7:00〜8:00 | パン・シリアル・卵料理・ヨーグルトなど |
| 昼食 | 11:30〜13:00 | 日替わりメイン+サラダバー |
| 夕食 | 17:30〜19:00 | 肉料理・パスタ・ベジタリアンメニューなど |
学校によっては食堂の混雑時間を緩和するため生徒によって昼食時間をずらす学校が多いです。
ボーディングスクールの一日の時間についてこちらの記事にまとめてます。
メニューの特徴と日替わりスタイル

ボーディングスクールのメニューは「日替わり・多国籍」。
アメリカの学校なら、
- ハンバーガー
- ピザ
- パスタ
が定番ですが、
同時に
- アジア
- メキシカン
- イタリアン
- ベジタリアン
メニューも日ごとに変わります。
生徒はアプリでその日の献立をチェックできる学校もあり、人気メニューの日は長蛇の列ができるほど。
季節のイベント(サンクスギビングやハロウィン)では、特別メニューが出ることも。
クリスマス近くは七面鳥、ハロウィンの時期はパンプキンパイを
みんなで囲む光景は、まさにアメリカの学校生活の象徴です。

2. 「まずい」って本当?ボーディングスクールの食事の評判
味の満足度は学校によって大きく違う


「ボーディングスクールのご飯はまずい」とSNSで目にすることもありますが、
実際は学校による差が極端に大きいです。
名門校ではシェフが常駐し、地元産食材を使った本格的なメニューを提供する一方で、
小規模校や予算の限られた学校では冷凍食品中心の場合も。涙
またお米ではなく、ピザやパンなど小麦粉の炭水化物やポテトが中心。
留学生にとっては、味そのものより食文化の違いに驚くケースが多いのです。

最高に美味しい学校メシをご紹介
ボーディングスクールの中には、食堂に驚くほど力を入れている学校があります。
私の印象では、学年が上がるにつれてごはんの質がぐんと上がる傾向があり、
中学より高校、そして大学に近づくほど“レストラン並み”になる学校が多いです。
- University of Massachusetts–Amherst(UMass Amherst)
- Cornell University(コーネル大学)
- Bowdoin College(ボーディン・カレッジ)
- Washington University in St. Louis(ワシントン大学セントルイス校)
実際、年間で食堂運営に1億円以上をかけている学校も。
ボーディングスクールが正との環境に多大な資産をかけていることをこちらの記事にまとめてます。
朝から焼き立てパンの香りが漂い、昼はパスタやサラダバー、夜はステーキやスープバーなど、
メニューはまるでホテルビュッフェのよう。
専属のコックさんが常駐していて、日替わりで多国籍料理を提供してくれます。





また、アイスクリームがいつでも食べ放題という夢のような学校もあります。
食堂に行けなかった日や自由時間には、キャンパス内のカフェテリアで
サンドイッチやチーズトースト、スムージーなどの軽食を楽しむことも可能です。


うちの息子ワンダも高校に入ってから「ごはんが本当に美味しい!」と毎日幸せそう。
食事が楽しみになるだけで、学校生活全体が明るくなるのを感じます。
最近では、食事満足度が学校評価の一部に組み込まれるケースも増え、改善が進んでいます。
3.食事が合わなかったときの対策3選
食堂のシェフと仲良くなる

食事が合わなかったり、食堂の時間に間に合わないことが続くとき、
意外と効果的なのが「シェフと仲良くなること」です。
うちの息子ワンダも中学のとき、寮でなかなか満足に食事がとれず、
いつもお腹をすかせていた時期がありました。

成長期に満足に食べられないのは親として心配、、、
そこで食堂のシェフに話しかけてみたところ、
それ以来、クラブ活動のあとにリンゴやバナナを分けてもらうようになったそうです。


なんかチンパンジーみたいだけど、母としてはめちゃくちゃ有難いです!
フルーツは軽くて腹持ちもよく、
シェフ側にも負担がかからないため、こうした“裏技”は意外と現実的な対策になります。
どんな国でも「ごはんをつくる人」との関係は大切。
感謝のひとことや笑顔があれば、食生活はぐっと豊かになります。
朝ごはんをしっかり食べる

ボーディングスクールの食事が合わないと感じるとき、
まず意識したいのが「朝ごはんをしっかり食べること」です。
朝食は、ほとんどの学校で
- 卵料理
- ベーコン
- トースト
- シリアル
などが中心。
どこで食べても味の差が出にくく、ハズレが少ないのが特徴です。
また、
- ヨーグルト
- 牛乳
は市販メーカーの小分けカップが多いため、安心して食べられる「安定の味」でもあります。
ビタミン補給には、
- オレンジジュース
- フルーツ
を積極的にとるのがおすすめ。
食事が合わなくても、朝の一杯でエネルギーを整えられるだけで
1日の集中力や気分がぐっと変わります。
“夜がダメでも朝で立て直す”――これは留学生の鉄則です。
非常食を用意しておく

留学生活では、勉強・スポーツ・成長期の体づくりなど、
とにかくエネルギーを使う場面が多いものです。
だからこそ「食べること」はすべての源。
お腹が空いたときにすぐ食べられる非常食を準備しておくのは、
見た目以上に大事な“生活スキル”です。
おすすめの方法はこの3つ👇
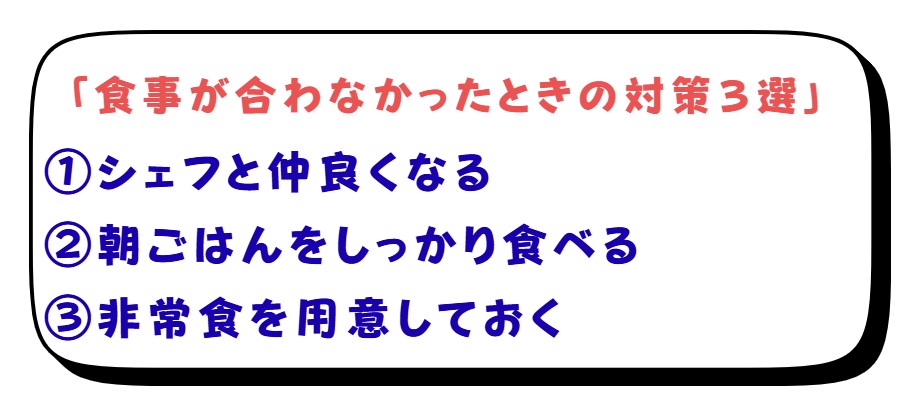
① アメリカのAmazonで注文して送ってもらう
現地のAmazonでも、カップラーメンやインスタント食品が手軽に買えます。
学校宛に配送してもらえば、いざという時に安心。
② 日本から持っていく
特におすすめはレンチンごはん。
寮にはほぼ必ず電子レンジがあり、温かいごはんは心までほっとします。
ふりかけをひとつ添えるだけで、立派な“癒しの夜食”に。
③ 腹持ちのいいお菓子を常備する
おせんべいは軽くて割れにくく、日持ちも抜群。
小腹を満たすのにぴったりです。
「空腹=集中力低下」につながるのは万国共通。
非常食をうまく活用することで、慣れない環境でも自分のペースを保てます。
4. 健康と栄養面のサポート体制
専属シェフ・栄養士の役割

ボーディングスクールの多くには、専属シェフや管理栄養士が常駐しています。
生徒の年齢層や活動量に合わせ、カロリー・タンパク質・ビタミンのバランスを考えた献立が組まれます。
特にスポーツが盛んな学校では、運動部員のために高タンパク食や補食コーナーが設置されていることも。
また、生徒が直接意見を出せる「Food Committee(食事委員会)」を設けている学校もあり、改善提案が反映される仕組みが整っています。
これはアメリカ教育らしい“生徒主体”の仕組みであり、食育にもつながっています。
食物アレルギー・宗教食への対応
アレルギー対応は年々厳格化しています。
ピーナッツや乳製品、グルテンなどの主要アレルゲンを明示する学校が多く、専用コーナーで代替食を提供。
宗教上の理由で豚肉や牛肉を避ける生徒にも配慮し、
- ハラール
- コーシャ
- ベジタリアン
といった区分を明確にしています。
留学前の健康調査フォームでは、アレルギーや食制限を必ず申告します。
この時に詳細(発症歴・医師診断書・エピペンの有無)を添えておくと、入学後のトラブルを防げます。
日本よりも「自己申告→学校が制度で守る」文化が浸透しているため、保護者としても安心できる部分です。
5. 留学生のリアルな食生活体験談
寮での週末ブランチ事情
平日の朝食は軽く済ませる生徒が多い分、週末のブランチはみんなの楽しみ。
- パンケーキ
- オムレツ
- ベーコン
- スムージー
などが並び、ゆったりとした音楽の中で友人と語り合う時間はまるでカフェのようです。
また、アメリカでは「食べながら勉強」が当たり前。
寮のラウンジでお菓子をつまみながら課題をする姿も珍しくありません。
こうした“食と学びが地続き”の文化は、日本の学校との大きな違いといえます。
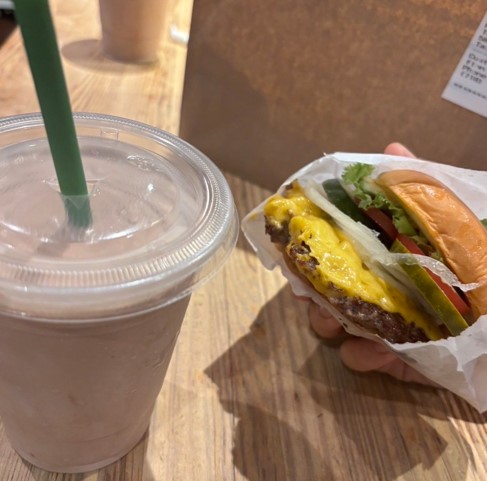

外食やデリバリー、友人との食事文化
週末外出許可(パーミッション)が出ると、街へ出て外食する生徒もいます。
アメリカでは「食べること=交流すること」。
友人やホストファミリーとの食事を通して、マナーや文化を自然に学ぶ機会にもなります。


6. ボーディングスクール選びで「食」は重要?
食事満足度が生活満足度に直結する理由
長期留学では「どんな食事が出るか」は、学業と同じくらい重要なポイントです。
食事は健康だけでなく、心の安定や社交の場としても大きな役割を持っています。
特に思春期の留学生にとって、食堂での時間は“家族の食卓の代わり”でもあります。
食事が合わないと、エネルギー不足やホームシックを引き起こすことも。
逆に食堂が楽しい場であれば、学校生活全体が明るく感じられます。
留学説明会などで「食堂の写真」「食事の口コミ」をチェックするのは、地味ですがとても大切な情報収集です。
学校選びのときに食事面をチェックするポイント
- ミールプランの種類(ブッフェ式か固定メニューか)
- ベジタリアン・ハラール対応の有無
- 食物アレルギーへの対応体制
- 食材の産地(ローカルファームとの提携など)
- 学生からの食事満足度・口コミ
オープンキャンパスやファミリーウィークエンドで実際に食べてみると、雰囲気も味もリアルにわかります。
「食堂が明るくて会話が多い学校=生活の質が高い学校」と考えて間違いありません。
8. まとめ:ボーディングスクールの食事は「生活の一部」
留学の成功を左右するのは、学力や英語力だけではありません。
「毎日をどう過ごすか」=生活の質をつくる要素こそが、海外での成長を支えます。
ボーディングスクールの食事は、その中心にあります。
食堂はただの食事スペースではなく、文化を学び、友情を育み、自立を体感する場。
そしてそこには、母国の味を懐かしみながらも、新しい世界の味に心を開いていく留学生たちの姿があります。
最初は「口に合わない」と感じても、半年後には自分の好きな組み合わせを見つけ、
1年後には「この学校の味が恋しい」と思えるようになる。
食は変化そのものを受け入れるプロセスです。
留学を考える方へ。
「食事」という小さな視点の中に、異文化理解や人間関係、そして生きる力が詰まっています。
ボーディングスクールの食卓は、未来へ続く学びの第一歩です。
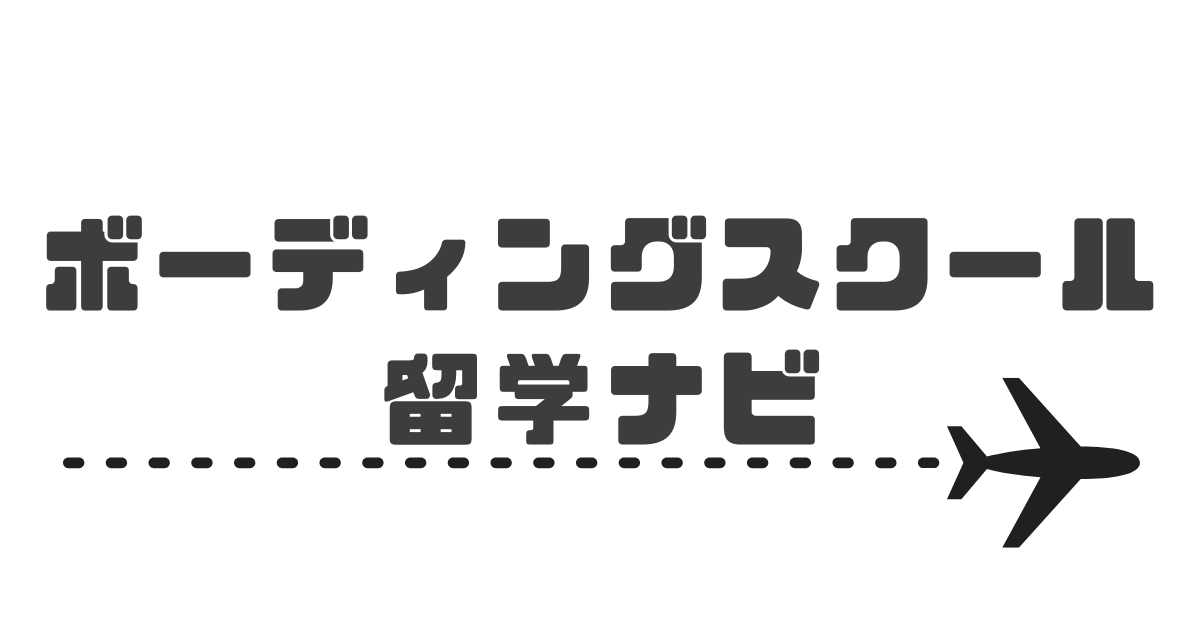



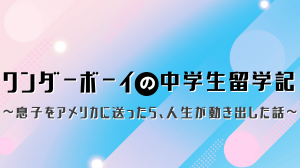

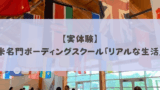
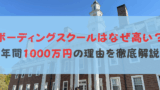
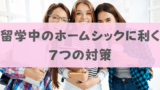
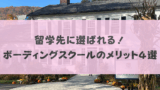
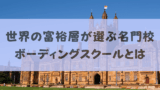
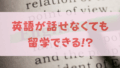
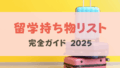
コメント